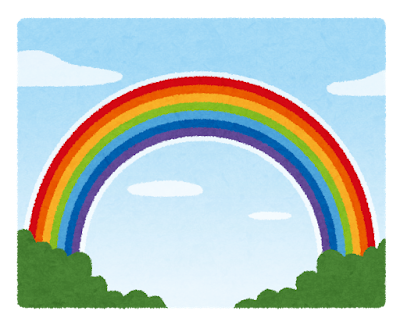梅雨時期の熱中症に要注意!!
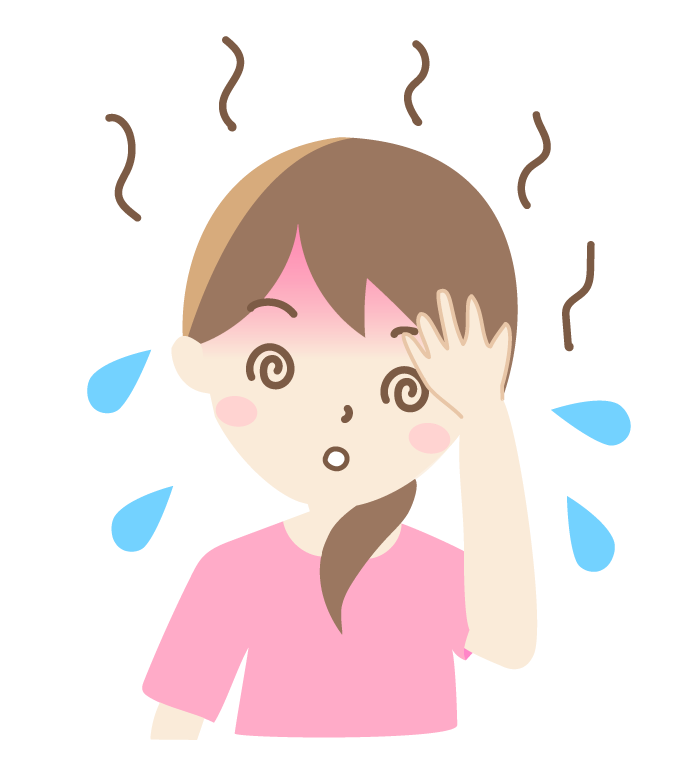
「熱中症は真夏の気温が高い日になるもの」と思い込んでいないですか?
確かに熱中症発生のピークは7~8月ですが、実は、発生数が増え始めるのは5~6月なのです。梅雨の晴れ間、梅雨明け直後など、身体がまだ高温多湿に順応できていないタイミングで急に気温が上がったり、蒸し暑くなったりすると、熱中症発生のリスクが高まります。
6月の熱中症
6月~7月の梅雨、低気圧通過直後などで高温多湿になるときです。
そして盲点になるのは、熱中症になりやすい時間帯。実は1日の中で最も気温が高くなる時間帯ではなく午前9時~11時です。この時間帯は急な気温上昇カーブを描くため、身体の体温調節機能が環境の変化に追いつかず、熱中症の発生事例が多くなるのです。
特に梅雨の晴れ間や梅雨明けの時期は要注意です。
熱中症の代表的な初期症状として、めまい(目眩、眩暈)や立ちくらみ、一時的な失神があります。 気温や湿度が高い環境のなかで、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、体に力が入らない、ぐったりする、呼びかけへの反応がおかしい、けいれんがある、まっすぐに走れない・歩けない、体が熱いなどの症状がみられたときには、すぐに熱中症が疑われます。

熱中症 こんな方は要注意!
・子ども・・・特に体温調節機能が十分に発達していない乳幼児は、大人よりも熱中症にかかりやすいといわれています。子どもは、大人より体重あたりの基礎代謝が高く、体温も高いのが特徴です。大人と比べて、汗腺が未発達なため、うまく体温調節をすることができません。
・高齢者・・・高齢者の方は温度に対する感覚が弱くなるため、室内でも熱中症にかかりやすいといわれています。加齢に伴い発汗などの体温調節機能は低下します。加齢に伴う活動性の低下は体温調節機能を増悪させる要因にもなります。
肥満傾向の人、体力不足の人、体調の悪い人、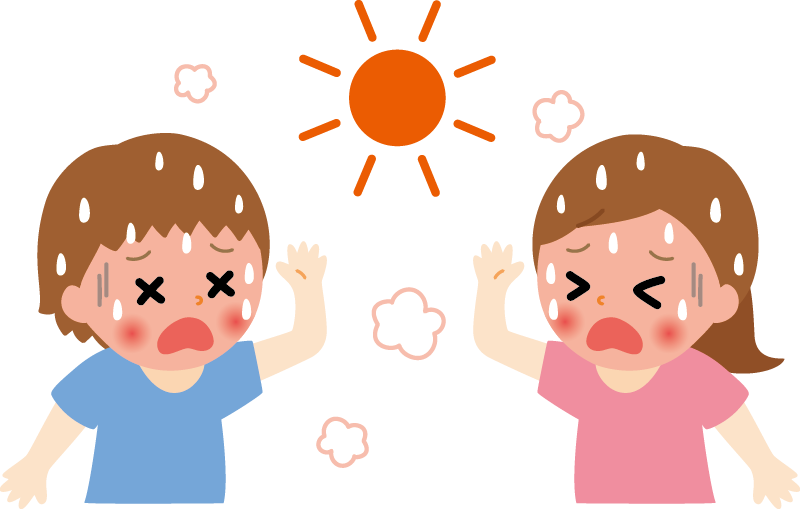
持病(糖尿病,心臓病,精神疾患等)のある人なども要注意です。 
熱中症対策
熱中症対策としての第一は「こまめな水分補給」です。 2%の水分を失うと強い喉の渇きやめまい、吐き気が起こります。 6%の水分を失うと手足の震えやふらつき、頭痛などの脱水症状が現れます。人は身体の60%が水分でできています。身体の6%の水分を失うと頭痛や体温の上昇などの脱水症状が現れます。
強い喉の渇きを感じるころには、すでに2%の水分が失われています。そのため、喉が渇いたと感じる前に、こまめな水分摂取が大切になります。
朝、自宅でできる一番の熱中症対策は、朝食を摂ることです。 時間や食欲がないからといって朝食を食べずに出かけてしまうと、体の水分タンクが空のまま活動することになるので、とても危険です。 朝食を摂ると水分だけでなく塩分も補給することができ、体温を下げる効果のある汗も出やすくなります。
衣服を工夫して、暑さを調節をしましょう。体の中に熱がこもって体温が上昇すると、熱中症の危険度が高まります。温度・湿度が高い日は、体の中に熱がこもらないように、衣服を工夫して暑さを調節しましょう。衣服の中や体の表面に風を通すことで、暑さを和らげることができます。襟元や袖口、裾などから空気が抜けるように、適度にゆとりのある服装がオススメです。また、綿や麻など通気性の良い素材や、吸湿性や速乾性に優れた素材を選ぶと良いでしょう。
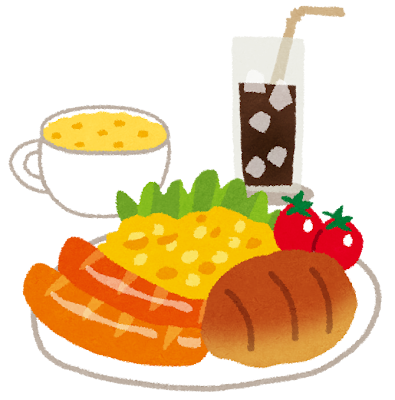


本格的に暑くなる前に、早めに暑さに対応できる身体にしておくのも大切なポイントの一つです。
そのためには、軽い運動や半身浴で汗をかくようにしましょう。晴れた日はちょっと遠回りして帰る、いつもより大股早歩きを意識してみるなど、ちょっとしたことから始めて、ぜひ汗をかくという機会を増やすようにしてみましょう。
梅雨の時期からしっかり熱中症対策をとり、元気に梅雨を乗り切りましょう♪